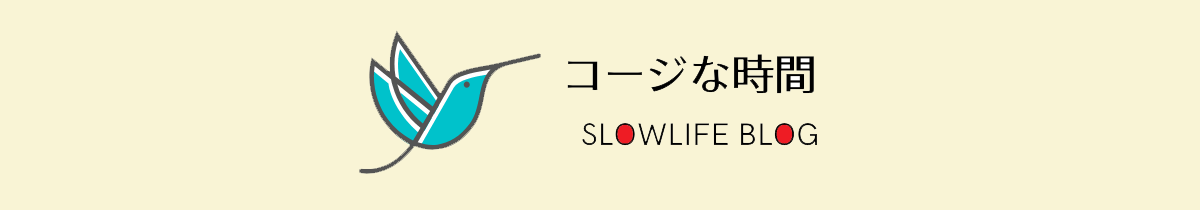2019年 金融庁の金融審議会「市場ワーキンググループ」の報告書。
「老後の30年間で約2000万円が不足する」と発表されました。
定年退職後は年金だけでは生活できない可能性があることを知って、将来のことをより具体的に考えるようになりました。
僕が将来に不安を感じたのは15年程前。
2007年から積立投資信託を開始。
その頃は老後2000万円問題なんてまだ言われていません。
2007年から積立投資信託を継続してきて今では良かったと思っています。

積立投資信託のシミュレーションがあるけど…
あれって本当なの?
結論から言うと…。
だいたい本当です!
順調に運用が進むと、ほぼシミュレーション通りになります。
僕が2007年からコツコツと続けてきた積立投資信託。
15年目時点ではどんなふうになったのか実例を公開します。

1968年生まれのアラフィフ。
2007年から積立投資信託を開始。
現在も継続中。
2019年から積立NISAを追加で開始。
積立投資信託 シミュレーション 本当?
インターネット上では投資信託の積立シミュレーションが公開されています。
そのうちのひとつ SBI証券の投資信託積立シミュレーションをしてみた結果が図の通り。

毎月3万円ずつ年利 3%で20年間積み立てた場合の結果です。
積立元本に対して、純粋に増えた額が約260万円。
20年で260万円増えたのだから1年で13万円ずつ増えたことになります。
普通預金をしていて年利で13万円ももらえるでしょうか?
投資信託の威力はスゴイ!
でも…
これって本当?
本当です!
我が家の積立投資信託の条件を入力したところ…。
我が家の現状とほぼ同じ結果を示しました。
積立投資信託 15年目の利益はどのくらいになるのか?
15年間コツコツと積み立てた投資信託。
利益は一体どのくらいになるのでしょうか?
積立投資信託 15年目の評価
我が家の積立投資信託15年目の資産評価は…。
単純に銀行貯金で積み立てるよりも良い結果が出ています。
具体的な総資産は公開できませんが…。
2021年 1年間の結果は次の通りでした。
- 1ヶ月の積立金額は2007年からずっと同額。
- 積立金以外の1年間の評価利益はプラス240万円。
いつもと同じようにコツコツ積み立てているだけで、積立金以外で1年間に240万円増えたことになります。
つまり1ヶ月あたり20万円ずつ貯金したのと同じと言えます。
積立投資信託を15年続けるとこんなふうになります。
もちろん、運用する投資信託の種類や、積立金額などによって違いがあります。
しかも、あくまでその時点の評価です。
今後、経済状況が急変するようなことが起こればどうなるかわかりません。
将来何が起こるか誰も予測はできないのです。
実際、我が家の積立投資信託は順風満帆だったわけではありません。
投資信託のリスク
投資信託にはリスクはつきものです。
15年の積立の間に2回のピンチがありました。
リーマンショック(2008年)
積立投資信託を始めたのが2007年。
毎月一定の金額をコツコツと積み立てました。
投資信託の評価額が積立金額よりプラスになったとき、投資信託は凄いと感じました。
ところが!
2008年リーマンショックが起きました。
世界同時株安。
日本企業の株価を表す日経平均株価がどんどん下がりました。
僕が積立投資信託を始めた頃の日経平均株価は12,000円くらい。
リーマンショックの時はあっという間に8,000円台まで下落しました。
当然、僕たちが積み立ててきた投資信託の評価額もどんどん下がり…
一番下がった時はマイナス30万円
マイナス30万円の評価は痛かった。
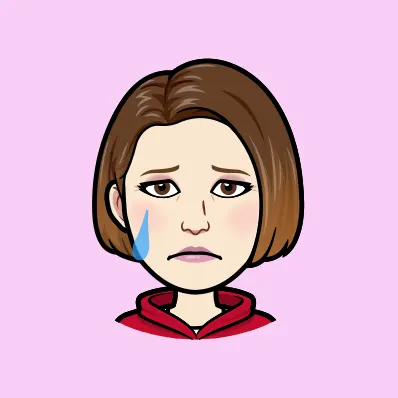
積み立てているのにお金が減るってどういうこと?
もうやめようよ…。
当然の反応です。
これが、投資信託のリスクです。
積み立てたお金が減ってしまう元本割れです。
正直、かなり凹みました(悲)
僕が読んだ本の中に「積立投資信託は、長期継続で効果を発揮する」とありました。
それに、これはあくまでその時点の評価額。
だから回復する可能性もあると前向きに考えました。
投資信託を始めて1年くらいでやめてしまうのは判断が早すぎると考えたのです。
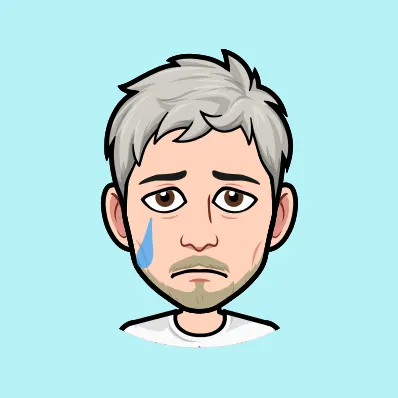
投資信託は長期で評価するもの。
だからもう少し様子見させてくれないかな。
5年、10年で評価したいんだけど…
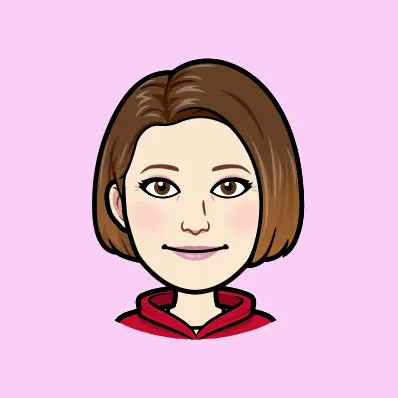
うん!分かった!
もう少し頑張ってみようか。
妻の寛大さが本当にありがたいと思いました。
株安ということは、積立金額が同じでも購入できる口数が多くなります。
口数が多く買える状況は、逆にチャンスなのでは?と考えました。
日経平均株価が8000円に落ち込んだ時も、迷うことなく積立を続けました。
その結果、たくさんの口数を保有することができました。
2021年8月の日経平均株価は27500円くらい。
リーマンショック時と比べて3倍以上になっています。
つまり、日本企業だけ見ても株価は全体的に上がり、企業が成長して経済が回っていることがわかります。
経済の回復に合わせて、我が家の積立投資信託評価も回復しました。
コロナショック(2020年)
コロナが流行した始め頃、感染防止のため休業する企業が多くなりました。
その結果、経済が冷え込むことに…。
感染対策に慣れてくると対策をしながら営業する企業も出始めました。
それにより経済も徐々に回復しました。
企業の努力はスゴイ!。
ただ、業種によっては休業や営業時間短縮の要請があり。
活動できない企業もありました。
そういう人たちの協力もあって、感染拡大が抑えられながら経済状況が少しずつ回復したことを忘れてはなりません。
我が家の積立投資信託もコロナショックの影響を受けました。
損失の割合は、2年前くらいの資産状況に戻された印象。
コロナショックの2020年には我が家の積立額がある程度あり、基盤ができていたため耐えることができました。
経済の回復に合わせて、我が家の積立投資信託評価も回復しました。

まとめ
15年目の我が家の積立投資信託の状況を例に積立投資信託のシミュレーションはだいたい本当であることを伝えました。
だいたい本当というのは投資信託には必ずリスクがあるからです。
シミュレーションは順調にいくとこのくらいになるという目安だと考えてください。
積立投資信託は長期継続で効果が発揮されます。
15年続けているので実感があります。
定年退職後、年金だけでは生活できないリスクがさまざまなメディアで報じられています。
老後に限らず、安定した資金を確保することは健やかに生きていくために必要な要素と言われています。
遅いということはありません。
興味関心を持った時がはじめ時だと思っています。
きちんと準備をして、少しでも早い時期に開始して長期継続すれば結果は現れます。
投資信託の始め方については別記事で書いています。
投資信託 始め方。僕はこうして投資信託を始めました。【体験談】
時間を味方につけましょう。
積立投資信託を実際にやってみて大事だと思うことは以下の通りです。
- ある程度の事前学習は惜しまずやる。
- 経済的に可能な範囲で行う。無理はしない。
- 家族合意で行う。
- 時間を味方につける。
最後まで読んでいただきありがとうございました。